こんにちは。
フィーリングテニスの戸村です。
さて、早速ですが今日のテーマです。
今日は「スライスが浮く理由と改善方法」
これについてお話しします。
フォアであれ、バックであれ。
「スライスを打つと浮いてしまう・・・」
こんな現象に悩まされている方は多いと思います。
では、なぜ、浮いてしまうのか?
まず、結論を言います。
スライスが浮いてしまう理由。
それは、ラケットヘッドが遅れているからです。
ここを改善しないと、抑えが効いたキレの良いスライスはいつまでも打てません。
一般的には、スライスが浮くとだいたい、下記の2点が問題だとされます。
・面が上を向き過ぎている
・下に切りすぎている
実はこの二つ、ほとんど関係ありません。
もちろん、影響が無いと言うわけではありません。
ラケット面やスイング軌道は必ずボールに影響を与えます。
ですが、ボールが浮いてしまう根本原因ではないんです。
本当の問題はインパクトの時にラケットヘッドが遅れている事です。
この状態になると、ラケット面が外に開く現象が起こります。
これがボールを抑える事が出来ない原因です。
テニスのスイングはスライスであれ、ドライブであれ、必ず、身体を中心とした回転運動になります。
その為に、ラケットヘッドは一時的に遅れたような状態になります。
ですが、良いプレーヤーはこのヘッドの動きがインパクトの瞬間には適切な状態に戻ってきます。
ところが、スライスが浮いてしまうプレーヤーは、ヘッドが遅れたまま、ボールとコンタクトします。
その為に、ラケット面が外を向いたまま当たってしまいます。
この状態では、いくらボールを抑えようとしても、ボールは逃げてしまいます。
これが下に抑えようとしても、抑えが効かない本当の原因です。
では、どうすれば、この問題は解消するのか?
実はインパクトでラケットヘッドが遅れてしまうプレーヤーには共通した問題があります。
それは、末端、つまり、ラケットまたはラケットヘッドを振ろうとしている事です。
このイメージで動くと必ずラケットヘッドは遅れて出てきます。
理由は身体(肩)を中心とした回転運動が大きくなるからです。
この問題を解消するには「二の腕」をしっかりと移動させる事。
そして、それに伴い「上腕」が適切に動いているか?
これがポイントになります。
スイングの始まりで二の腕、そして、上腕が適切に動くようになるとスイングは直線運動に近づける事が出来ます。
その結果、ラケットヘッドの遅れを解消できるようになります。
もちろん、バックスイング完了時のラケット面の向きやスイングの軌道も調整が必要です。
ですが、ラケットヘッドの遅れさえ、解消できれば、その調整は難しい事ではありません。
「ボールを捕らえる感覚」
「ボールを抑える感覚」
こういう感覚を体験できるからです。
この感覚が分かれば、スライスの回転量を増やしたければ、更に下に切れば回転量は増えます。
逆に回転量を減らしたければ、下ではなく、前に振れば良いだけです。
それに伴ってラケット面も自動的に調整されます。
「スライスが浮く問題」が中々解消しない人が一番困る事は、ボールの抑え方が分からない事です。
自分では抑えているつもりなのに、浮いてしまうわけですから「どうしたら良いのか分からない・・・」
こんな状態に陥っていると思います。
この状態から脱却するには、ラケット面の向きやスイング軌道ではなく、ラケットヘッドの遅れに注目してください。
その為には「二の腕」が適切に動いているか?
まずはここをチェックしてみてください。
スライスが浮くプレーヤーは、まず、間違いなくと言って良いほど、ここが適切に動いていません。
二の腕が適切に動き始めると、ラケットヘッドは遅れなくなります。
そしてボールに抑えが効くようになります。
良かったら参考にしてみてください。
本日のお話しは以上です。
いつも長文お読みいただいて本当にありがとうございます。

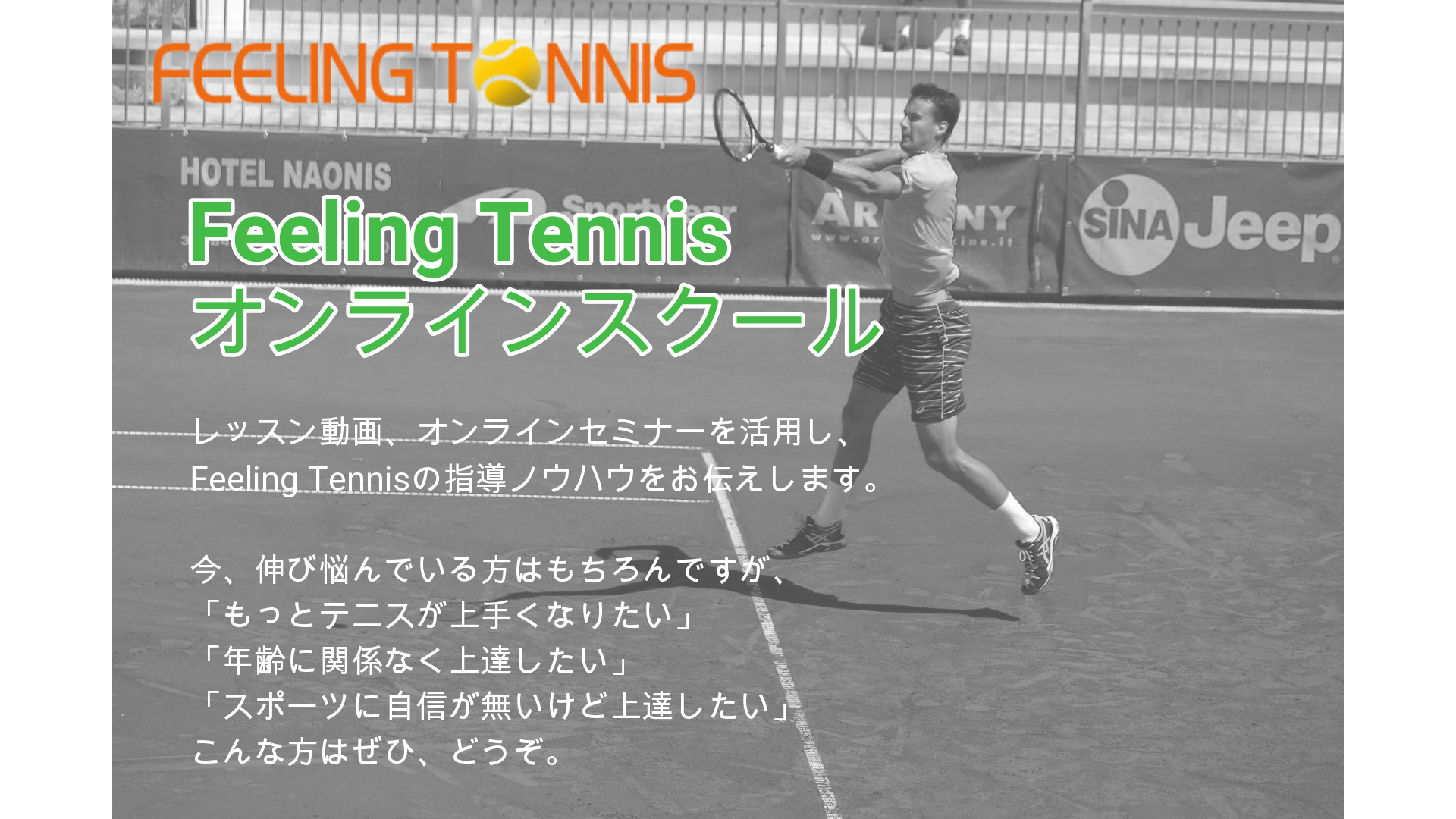







コメント